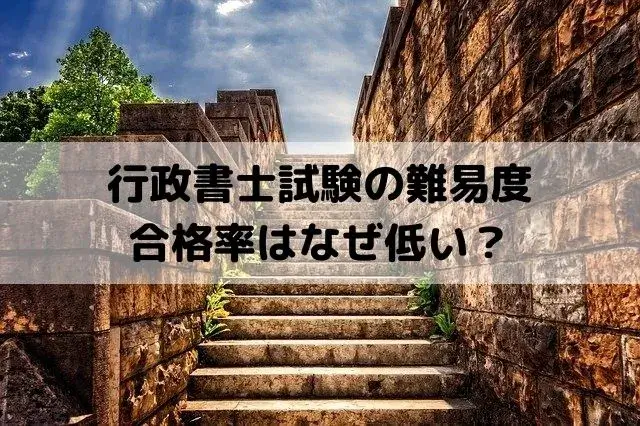「行政書士試験の難易度を知りたい」
「結局行政書士試験って難しいの?簡単なの?」
行政書士試験の難易度が実際どれくらいなのか正確に知りたいという人は少なくないのではないでしょうか。
ネットの情報だと難しいという人もいれば、簡単という人もいてどっちなのかわからないですよね。
これから行政書士試験の勉強を始めるにあたってはその難易度をある程度把握しておくことが大事です。
そこで本記事では、行政書士試験の難易度について様々な角度から説明していきます。
行政書士試験の難易度とは?
まず行政書士試験の難易度について説明していきます。
合格率
近年における行政書士試験の合格率の推移は以下の通りです。
| 平成28年度 | 10.0% |
| 平成29年度 | 15.7% |
| 平成30年度 | 12.7% |
| 令和元年度 | 11.5% |
| 令和2年度 | 10.7% |
参考:スタディング「行政書士試験の合格率と難易度を3分で解説」
上記の通り、10%程度の合格率で推移しています。
10人受けて1人しか受からない計算となるので、難しいと感じる人も少なくないでしょう。
しかし、合格率が低い理由としては、受験資格がなく、全員が合格ラインに達するほど十分な勉強をしているわけではないという側面があります。
合格率の低さほど競争は合格率ほど激しくないですので、法律初学者の方もぜひ挑戦していただきればと思います。
勉強時間
行政書士試験に合格するために必要な勉強時間は平均だと600時間から700時間程度です。
ここから前提知識や通信講座受講の有無などによって必要な勉強時間は少なくなったり、多くなったりします。
いずれにせよ、勉強期間にして半年から1年程度は要するので、まとまった学習計画を立てる必要がある試験です。
-

-
行政書士合格に必要な勉強時間とは?平均や最短はどれくらい?
続きを見る
試験の難しさ
行政書士試験自体の難しさとしては以下の点が挙げられます。
・足切り点がある
・記述問題がある
・試験範囲が広い
・一般知識問題がもある
・暗記だけでは対応できない
上記の通り、行政書士試験ならではの難しさがあります。
少なくとも、テキストを何回か読んで、ここ数年の過去問を解く程度では受かりません(少なくとも10年分はやりましょう)。
試験範囲が広くてどこまで学習するべきか迷いますし、足切りもあるため、捨て科目は作りづらいです。
長期的な学習計画を立てて、着実に知識を身につけていく必要があります。
-



-
行政書士に合格するための完全ロードマップ【法律初学者向け】
続きを見る
独学の難易度
行政書士試験自体は独学でも合格できる難易度です。
具体的には、市販のテキストや過去問集などを解いて、予備校の模試を受けるなどしていけば独学でもなんとかなります。
しかし、行政書士試験を何回も受験されている方もいるという事実もあります。
試験範囲が広く、法律という専門的な事柄を扱ってますので、独学だと難しいケースもあるでしょう。
独学で合格できるかは結局その人次第なので、独学でいくか、通信講座を受講するかはあらかじめよく検討したほうがいいと思います。
-


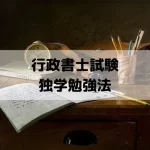
-
行政書士合格は独学では無理?注意すべきポイントを解説!
続きを見る
行政書士と他資格との難易度比較
本章では、行政書士と他資格を比較しつつ、難易度について説明していきます。
FP2級
FP2級学科の合格率は40%程度であり、必要な勉強時間も150時間から300時間程度なので、行政書士のほうが難易度が高いと言えます。
試験内容としてもFP2級は過去問を数年分こなせば合格ラインに達しやすく、対策が比較的容易です。
ちなみにFP2級の相続分野は行政書士の民法と試験範囲が重複してます。
-



-
FP2級と行政書士の難易度の違いはどれくらい?試験内容の差を紹介
続きを見る
宅建士
宅建士の合格率は10%後半で、必要な勉強時間は300時間から400時間程度となっており、FP2級よりは難易度が高く、行政書士よりは難易度が低いといったところです。
宅建士も受験資格がなく、年1回の試験であり、何回も受験している人も多いでしょうから受験層も決して低くないと思います。
ただ、宅建士は全ての問題がマークシートで記述問題がないので、試験自体の対策は行政書士より立てやすいでしょうし、選択肢をある程度絞れれば正解できるという点はあります。
-



-
行政書士と宅建の難易度の違いとは?どっちを受けるべき?
続きを見る
社会保険労務士
社会保険労務士の合格率は5%から8%ほどで、必要な勉強時間は1000時間以上とされており、行政書士より難易度はやや高いといった感じです。
ただ、社会保険労務士の試験には記述問題がなく、全問マークシートであるため、人によっては行政書士のほうが難しいと感じる人もいるかもしれません。
社会保険労務士は、学習量が多くて細かい数字や制度の暗記があり、足切り点もシビアですから行政書士以上に長期的な学習計画が必要です。
中小企業診断士
中小企業診断士試験はは1次試験と2次試験があり、2次試験まで考慮に入れると合格率は4%~5%ほどで、必要な勉強時間は1000時間~1500時間ほどですから行政書士よりは難易度が高くなってます。
2次試験には口述試験もあるため、行政書士とは違った難しさもあります。
司法書士
司法書士試験の合格率は3%ほどで、必要な勉強時間は3000時間以上とされており、行政書士よりもかなり難易度が高くなってます。
受験者のレベルも全体的に高くて競争が激しいので、一発合格も難しいです。
そのため、必要な勉強時間は3000時間以上と言いましたが、実際には何回も受験することになるので、その倍以上になることも少なくありません。
行政書士と司法書士は試験科目(憲法・民法・商法)が被っているので、ダブルライセンスを目指す人も多いと思いますが、難易度を考慮すると、まずは行政書士合格から目指すことをおすすめします。
-


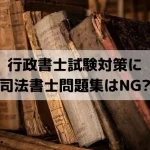
-
行政書士に司法書士の問題集やテキストは使うべきでない理由を解説
続きを見る
税理士
税理士は科目合格制度があり、1科目ずつ合格可能な試験です。
科目ごとの合格率は10%前後のものが多くなっており、合格率だけ見ると行政書士とあまり変わりませんが、同じ科目を何回も受けている受験生が多く、受験者のレベルが高い中での合格率なので、実際には行政書士よりも難易度は高いと言えます。
ちなみに税理士は行政書士を受験せずに行政書士登録が可能となってます。
行政書士の難易度が高いと感じたら通信講座の受講も検討しよう
行政書士試験は士業の中だと難易度は低いほうですが、一般的な資格からすると難易度は高いです。
市販の本をちょっと勉強した程度では受かりませんし、ある程度試験勉強慣れしていない難しいかもしれません。
まずは独学で勉強してみて、いけそうならそのまま独学でもいいですが、理解や暗記が全然できないようなら早めに通信講座の受講も検討することをおすすめします。
近年では、10万以下の安い行政書士通信講座の受講も多くなってますので、コスパよく学習できます。
-


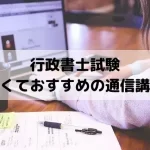
-
安い行政書士通信講座おすすめランキング!徹底比較しました!【2023年3月最新】
続きを見る
まとめ
行政書士の難易度を紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか。
試験に一発で合格するためにも試験の難易度をある程度把握した上で、十分な勉強時間を確保し、学習計画を立てていくことが大事です。
独学か通信講座を受講するかによっても、学習の進み具合は変わってきますから試験勉強に自信がないという人は通信講座の受講も早めに検討するようにしましょう。